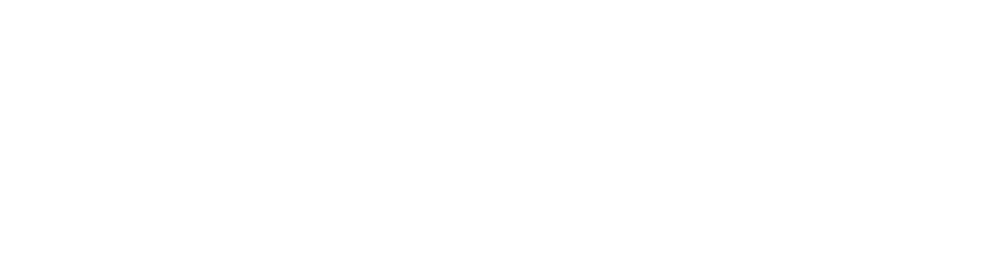Interview No.41 JIN YIJIE
物資理工学院
東京科学大学道信研究室のJIN YIJIEと申します。趣味は旅行と風景写真で、日本ではほぼ全都道府県(鹿児島を除く)、海外ではアフリカと南極以外を巡りました。特に早朝の海岸で捉える朝陽のグラデーションがお気に入りです。休日はキャンパス内の広大な緑道を仲間と散歩し、近隣の店で学生同士の交流を楽しんでいます。東京科学大学の最大の魅力は、最先端設備と自然が調和した学習環境です。広々としたキャンパス内には緑豊かな休憩スペースが点在し、研究の合間にリフレッシュできます。

研究概要 / Research Outline
森林資源はカーボンニュートラルな資源で、その成分はセルロース、ヘミセルロース、リグニンから成ります。これまでの研究において、森林資源の主要成分であるリグニンに注目し、リグニン分解微生物Sphingobium sp. SYK-6株が様々な構造からなるリグニンを代謝する際に得られる2-ピロン-4,6-ジカルボン酸(PDC)を原料とした新規ポリマーの生分解性評価を実施しています。BOD測定やISO規格に基づく分解試験に加え、池水と深層・浅層海水環境での比較実験を通じて、材料の環境適合性を多角的に分析。これらの生分解性に関する評価は、環境負荷低減に貢献するPDC材料開発の基礎となる重要な知見を提供します。既存の生分解性材料との性能比較から、持続可能な社会実現への貢献可能性を探求しています。博士課程一年目の研究成果は論文としてまとめられ、RSC Sustainability誌に掲載された。さらに、別の論文がPolymer Chemistry誌に掲載された。

持続可能な未来への架け橋及び研究が拓く新たな可能性
私の研究人生を決定づけたのは、2008年から始めた世界旅行での衝撃的な体験でした。ハワイ・ワイキキ沖合で、海面に漂うペットボトルやレジ袋が陽光にゆらめく光景は忘れられません。観光客でにぎわう海岸から500メートルほど離れた海域に、文明の影が静かに広がっていました。地中海クルーズでは、飛行機で遠洋域に点在するプラスチック片が波間に不自然な輝きを放つ光景を目撃し、環境問題の複雑さを実感したのです。これらの体験が、単なる環境問題の「可視化」を超えて、分子レベルの解決策を求める原動力となり、「持続可能な素材開発」の必要性を強く意識するようになりました。
現在取り組んでいるPDCポリマーの研究は、まさにこの問題解決に向けた挑戦です。森林資源に含まれるリグニンをSphingobium sp. SYK-6株で分解する過程で生成される2-ピロン-4,6-ジカルボン酸(PDC)に注目しました。この微生物はリグニンの複雑な芳香族構造を効率的に代謝し、TCA回路へと導く優れた能力を持っています。私はこの天然由来のPDCを原料に、従来の石油系プラスチックに代わる新規ポリマーの開発を進めているのです。
現在進めている研究では、植物由来成分から開発した新材料の分解速度をISO規格で測定しています。例えば池水環境での試験では、従来材料より早い速度で分解が進むことを確認できました。具体的には、学校近くの洗足池で採取した池水を用いた実験では、PDCポリマーが三ヶ月間で重量の60%を消失し、興味深いデータが得られました。物質文明の発展は、必然的に新たな課題を生み出します。私が取り組む生分解材料研究の真の意義は、単に環境負荷を軽減するだけではありません。自然界の循環システムと人類の技術革新を調和させる新たな共存様式を提示することにあります。例えば医療分野では、生体吸収性材料が手術用縫合糸として活用されています。このように、環境技術の発展は他の分野のイノベーションを触発する可能性を秘めているのです。
研究活動を通じて得られる最大の喜びは、小さな発見が社会の大きな変化へと繋がる可能性を感じられる瞬間です。実験室で得られた分解データの一つ一つが、海辺の生態系保護に直接役立つかもしれない。例えば先月、焼津市から取った試験水での生分解試験より、すごく面白いデータが取れました。この事実は、自然界における分解プロセスの冗長性を証明し、材料設計における生分解性の普遍性を高める重要な手がかりとなります。このような想像力こそが、研究者にとって最も大切な資質ではないでしょうか。また、予期せぬ失敗から生まれる発見が、全く異なる分野の問題解決に応用されるケースも少なくありません。科学の持つこの普遍性が、研究活動の醍醐味と言えるでしょう。
持続可能な社会の実現は、特定の分野だけでは成し得ません。基礎研究の成果が異分野へ展開されるプロセスこそ、現代の研究者に求められる視野の広さを物語っているでしょう。環境技術の進歩が経済活動を活性化させ、教育現場に新たな学びを提供し、地域コミュニティの結束を強めます。このような好循環の創出こそが、現代の研究者に課せられた使命です。森林資源のカーボンニュートラル性に関して、リグニン分解プロセスから得られるPDCの大量生産技術が確立すれば、石油由来化学品の代替としてカーボンニュートラル社会の実現に寄与できます。森林資源の有効活用を通じ、材料科学が林業の活性化と生態系保全の両立を可能にし、これこそが、私が目指す真のサステナビリティです。

メッセージ / Message
SPRING/BOOSTの仲間の皆様へ。研究を続ける原動力となる最初のきっかけを大切にしていますか? 就職やスキルアップといった目標も、社会を変えたいという志も、どれも尊い原動力です。困難に直面した時は、研究を始めた頃の純粋な疑問を思い出してください。私たちの積み重ねが、いつか社会のパズルを埋める一片となるよう。皆さんだけが描ける未来の図像を、どうか大切に育んでください。