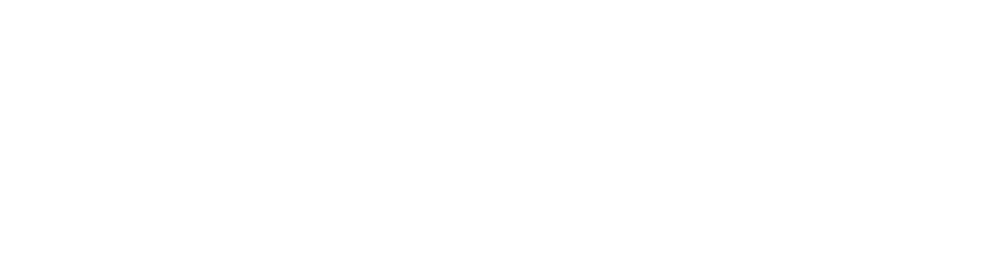Interview No.59 田村汐里
生命理工学院
東京科学大学生命理工学院生命理工学系に在籍しております、田村汐里です。趣味は、映画を観たり、旅行に行き自然に触れたりすることです。


Research Outline
生体外で臓器機能を再現できる培養モデルの開発を目的として研究をしています。特に、薬物の吸収・代謝において重要な役割を担う腸と肝臓に焦点を当て、それぞれの組織を模倣した腸モデルおよび肝臓モデルの構築に取り組んでいます。近年、腸内細菌やその代謝産物が薬物動態に大きく関与することが明らかとなり、これらを含めた評価系の重要性が増しています。しかし従来の培養モデルでは、腸内細菌の過剰な増殖や、細胞との生活環境の違いにより、腸内細菌と細胞の共培養は困難とされてきました。そこで、我々は、動的培養と組織特有の微小環境の再現を目的とした、二層構造のマイクロ流体デバイスを企業と共同開発しました。本デバイスにより、培地に流速を与えることで腸内細菌の増殖を制御し、さらに二層構造によって腸組織と肝組織に類似した環境を再現することができると考えました。本モデルを用いることで、腸内細菌との安定した共培養が実現し、将来的には腸内細菌研究や非臨床試験モデルとしての応用が期待されます。
〇 動機
私はこれまで、自身の研究内容を他者に伝える際、特に分野外の人に対してわかりやすく説明することに課題を感じてきました。専門用語に頼らずに本質を伝える能力や、相手の理解度に応じて説明の深度を調整する力が不足しており、研究者として必要な「伝える力」に不安を抱いていました。将来的にアカデミアにとどまらず産学連携や国際共同研究などに関わるためにも、プレゼンテーション能力や説明力、そして多様な背景をもつ研究者とのコミュニケーション能力の向上が不可欠であると強く感じるようになりました。
○ 取り組み
この課題を克服するため、私は積極的に学会に参加し、研究成果の発表を通じてプレゼンテーション力を磨いてきました。特に、分野外の聴衆にも伝わるように図や例え話を工夫し、資料作成の際には「視覚的に理解しやすい構成」を意識しました。さらに研究室内では定期的に発表練習を行い、指導教員や同僚からのフィードバックを受けながら改善を重ねました。
また、グローバルな視点と英語による発信力を養うことを目的に、国内学会だけでなく国際学会にも積極的に参加しました。その際、費用面の支援として、本フェローシップ制度の「学外研鑽プラス」を活用したほか、外部財団の国際会議参加助成にも自ら申請し、競争的に獲得することで、国際的な場での発表機会を実現しました。国際学会では、英語でのプレゼン資料の作成や質疑応答の練習を重ね、語学的な準備にも力を入れました。
○ 成果
これらの取り組みを通じて、私は徐々に研究を客観的に捉える視点を持てるようになり、聞き手に応じた説明ができるようになってきました。英語での発表経験によって語彙力や言い回しの幅が広がり、英語論文の読解速度も向上しました。実際に、国際学会での発表後には、他国の研究者から興味深い質問やアドバイスを受け、それが新たな仮説の着想や研究計画の修正につながるなど、貴重な学びと刺激を得ることができました。
○ 今後の展望
今後も学会での発表を継続し、分野や言語を問わず研究成果を正確かつ魅力的に伝えられる能力をさらに磨いていきたいと考えています。特に、分野融合的な研究や産学連携を進める上では、異なるバックグラウンドを持つ相手との円滑なコミュニケーションが鍵となるため、対話力と論理的な説明力の向上に引き続き取り組んでいきたいと考えています。
Message
国際学会は「英語だから大変そう」と感じるかもしれませんが、準備を重ねることで英語力や発表力だけでなく、研究の視野や人とのつながりも大きく広がります。実際に参加してみると、得られる刺激や学びは想像以上です。少しでも興味があれば、ぜひ挑戦してみてください。その経験は必ず今後の研究やキャリアに活きてくると思います